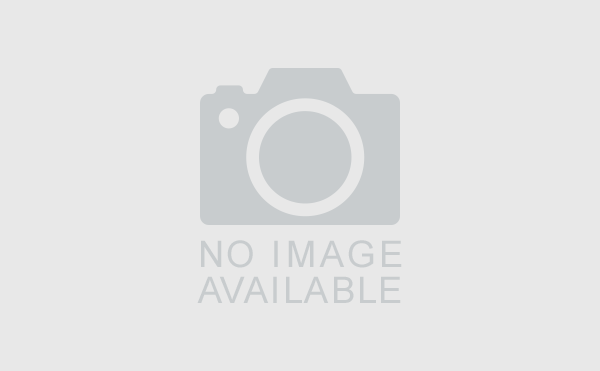相続人に認知症の方がいたら
厚生労働省の統計では、2030年には認知症の患者数は約523万人で高齢者の約14%、2040年には約584万人で高齢者の約15%、6.7人に1人を占めると予想されています。
認知症の有病率は年齢とともに急上昇することが知られており、80歳代の後半では男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎると男性の51%、女性の84%が認知症であるとされています。
遺産分割協議はできない
認知症などで判断能力が低下していると、意思表示することはできないので、遺産分割協議ができません。
軽度の認知症の場合、遺産分割時の状態で意思能力が認められればその本人が遺産分割協議をすることが可能です。この場合は、後日問題にならないように遺産分割時の医師の診断書等、意思能力に問題がなかったことを根拠付ける資料を用意しておく必要があります。
意思能力がない相続人がいるにも関わらず遺産分割協議書を作成した場合には、私文書偽造罪にあたる可能性があり、この場合、3か月以上5年以下の懲役に処せられます。(刑法159条)
- 預貯金、有価証券
- 凍結解除は、請求用紙に相続人全員の署名と印鑑証明があれば可能ですが、認知症の方の署名押印はできないため請求できません。当然、認知症の方の代筆は私文書偽造罪になります。
- なお、「預貯金の仮払い制度」があり、それぞれの相続人が150万円を上限として、その銀行にある「預貯金額×3分の1×法定相続分」まで、払戻しすることはできます。これは、葬儀費用や生活費、相続債務の返済などの負担を軽減することを目的として最近できたものです。
- 不動産
- 賃貸も売却もできません。契約書には認知症の方の署名押印はできませんし、代筆は私文書偽造罪になります。
- 偽造した遺産分割協議書を使って法務局で不動産の相続登記をした場合には公正証書原本不実記載罪にあたる可能性があり、5年以下の懲役は又は50万円以下の罰金に処せられます。(刑法157条)
相続放棄
相続財産で債務が多い場合は3か月以内に相続放棄することができますが、相続人に認知症の方がいると法律行為ができなくなります。他の相続人が本人に代わって相続放棄の申し立てをしようとしても、家庭裁判所から受理されません。
法定相続で分割する方法
- 預貯金
- 遺産分割協議ができなければ、「自分の法定相続分だけを請求する」ことはできません。
- 不動産
- 不動産については「法定相続分」に分ける旨の登記は相続人の1人からすることができます。この場合には遺産分割協議もなく後見制度を利用せずに進めることも可能です。
- 「法定相続分で登記する」ということは、相続人全員の共有となります。共有者全員の合意が必要なので、認知症の方がいると売却や賃貸等はできません。
成年後見制度を利用する方法
このように相続人に認知症の方がいると遺産分割協議ができませんが、成年後見制度を利用すれば、認知症の方の代わりに後見人が遺産分割協議や相続放棄をすることができます。
成年後見人を誰にするかの決定権は、家庭裁判所が持っているので、親族は後見人に選ばれず、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれてしまう可能性が高いです。
専門家が後見人になると毎月報酬が発生します。目安は最低月2万円、財産額によっては月5~6万円になることもあります。認知症の方が亡くなるまで後見人に報酬を支払わなければなりません。 預貯金は、原則として「成年被後見人 ○○△△、成年後見人 ●●■■」というように、後見人と被後見人の連名にして成年後見人が管理します。介護の契約や施設・病院との契約などの法律行為も後見人が本人の代理人となって行います。
- 手続き
- 後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる場合、手続きには1~3カ月ほどかかります。
- 費用
- ①申立手数料(収入印紙)800円、②登記手数料2,600円、③予納郵便切手3,270円分④診断書の作成費用5000円~1万円程度、⑤鑑定費用5万円~10万円程度、⑥戸籍や住民票写し等の書類取得費1,000円~2,000円程度、⑦弁護士・司法書士に依頼する場合の費用10万円~30万円程度
- 遺産分割協議
- 後見人の使命は「認知症の方の財産を守ること」なので法定相続分を死守します。したがって、ほかの相続人の意図通りになるとは限りません。
特別代理人制度を利用する方法
成年後見人は認知症の方の財産を管理するため、その方が亡くなるまで関与することになりますが、この特別代理人は、家庭裁判所が一時的に成年被後見人を代理する権限を与えるというのです。
この場合でも遺産分割協議書では成年被後見人の取得割合を法定相続分未満とすることは原則としてできません。
協議せずに放置する方法
成年後見人、法定代理人を立てずに認知症の方が亡くなるまで放置し、亡くなった後に相続人で、遺産分割を協議することも可能です。
しかし、遺産の相続手続きができないため、預貯金や有価証券が凍結されたままとなり、遺産を使えません。
このため、相続人が費用を立て替えたりしなければならず、その期間がいつまでかわからないのもデメリットとなります。
相続税はどうなる?
相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内となっています。遺産分割協議が整わない場合は、法定相続分で申告することになります。
相続人に認知症の方がいる場合、いろいろな特例が使えません。
ただし、3年以内に遺産分割協議が見込めそうな場合は、分割見込書を添付して申告しておき、将来的に遺産分割が確定した時点で4ヶ月以内に修正申告(更正の請求)をすればこれらの特例の適用が可能となります。
- 小規模宅地等の特例
- 相続する居住用や事業用の土地の評価額を最大8割まで減額できる制度です。
- 配偶者の税額の軽減
- 配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば相続税が課税されない制度です。 もし、1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。
今回は認知症の相続人がいた場合について説明しました。参考にしていただければありがたいです。