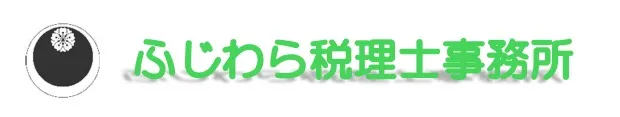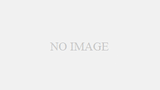戸籍謄本は、誰が法定相続人であるかを確認するためのもので、相続税の申告、不動産の相続登記、預貯金や証券口座の名義変更などの手続きを行う際に必要です。
戸籍謄本はどこで手に入れる?
今まで戸籍謄本等の証明書を取得するためには、亡くなった方の本籍地の市役所窓口へ申請をする必要がありました。本籍地が生前に異動していればその前の本籍地の市役所へ申請するなど、手続きが面倒でした。
しかし、2024年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、全国各地にある戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになりました。(内容により一部請求できないものがあります。)
申請できる人
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪などの戸籍謄本は請求できません。
また、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など第三者による請求もできません。
申請できる場所
役所窓口のみ
※郵送、代理人申請はできません
必要書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど申請者の顔写真付き身分証明書
戸籍謄本は誰のものが必要?
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。 戸籍謄本のほか、除籍謄本、改製原戸籍謄本と呼ぶものもあり、コンピューター化されている場合は、戸籍全部事項証明書、除籍事項証明書と言います。
戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない戸籍は取得できません。新旧本籍地の市区町村に請求する必要があります。その場合、更に請求すべき市区町村及び戸籍等を教えてもらい、別途当該市区町村に請求する必要があります。
請求する市区町村が遠隔地の場合、郵送により請求することができますが、 手数料の納付方法など具体的な方法は、その市区町村の戸籍担当の係に電話等で確認してください。
全ての法定相続人の戸籍謄本又は抄本
被相続人が亡くなった後に発行された戸籍謄本が必要です。
法定相続情報一覧図
亡くなった方の取引銀行に相続手続きをする際に戸籍謄本が必要ですが、銀行が複数あると、複数部用意するか、1部を使い回すなど時間と労力を要します。
そこで、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図を提出すると、それが「法定相続情報一覧図」として証明してもらえ、しかもその写しを無料で必要な通数を交付してもらえます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸籍謄本等の束を何度も各種窓口にそれぞれ提出する必要がなくなります。
この制度を利用することができる方は、被相続人(亡くなった方)の相続人(又はその相続人)です。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士 に依頼することができます。
相続税の申告は税理士にお任せください
相続税や贈与税、新規開業、事業や農業、不動産、土地建物の譲渡などの所得税・消費税の確定申告,記帳代行、税務調査はお任せください。
ご相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
電話でのお問い合わせは、080-5809-3394までご連絡ください。
- 不在あるいは来客中の場合がありますので、お越しの際は事前にご連絡ください。
- 営業時間:午前9:00–午後5:00
- 事前のご予約により、土日祝日も対応しています。
- 電話は営業時間外でも対応(土日OK)しています。AM8:00~PM6:00
- 応答がない場合は留守番電話へメッセージをお願いします。(営業目的の電話が多いため、着信だけでは折返しの電話は致しません。)