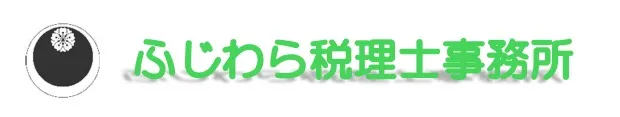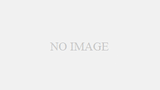相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。
戸籍謄本
亡くなられた人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
遺言書の有無の確認
遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書および法務局に保管された自筆証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
遺産と債務の確認
遺産と債務を調べておきます。葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。
財産の評価
土地や建物については、市役所固定資産税課から「名寄帳」を取り寄せます。固定資産税通知書では、固定資産税のかからない物件(道路など)が表示されていないので、後々の不動産登記の際に、不都合が生じます。
遺産の分割
遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
相続税の申告と納税
通常の場合は、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
相続財産が分割されていないとき
相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分で財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、相続税の特例である小規模宅地等の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できません。
その後、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。