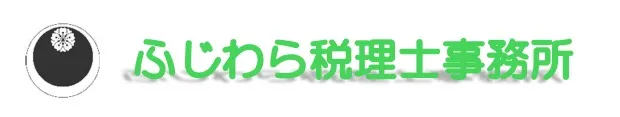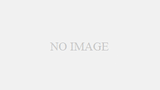法定相続人の配偶者や同居する子供など、生前に無償で療養看護その他の労務の提供をした場合、他の相続人に対して相応の権利を主張できるのでしょうか。
民法では、これを「寄与分」として寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるとされています。
寄与分として認められているもの
民法の第904条2項において、実際に寄与分として認められているのは、以下のものになります。
- 家事従事・・生前に被相続人の事業をほぼ無償(あるいは一般的な対価と比べて著しく低い対価)で役務を提供した場合
- 金銭等出資・・事業への資金援助や事業用資産の提供など
- 療養看護・・生前に被相続人を看護したことにより、本来ならば外部へ支払わなければならなかった看護費用などの支出が抑えられ、結果としてその分だけ相続財産の維持や形成に貢献した場合。病院への送り迎えだけでは該当しない。
- 扶養・・相続財産の維持や形成に貢献した場合
- 財産管理・・被相続人に代わって不動産の管理業務などを行っていた場合や、税金や修繕費などを被相続人に代わって負担していた場合
要件
- 相続人以外で、6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族に該当する者
- 療養看護や労務の提供が無償であったこと
- 特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に請求すること
寄与料の算定方法
まずは、関係者間の協議により決めます。しかし、意見対立などがあり、協議で金額を決められない場合は、家庭裁判所の調停・審理手続きの中で決める必要があります。
この特別寄与料の算定方法には、一つの目安として付添人の日当額療養看護の日数 × 裁量割合(0.5〜0.7)があります。
相続で認めてくれるか
特別な寄与と認められるハードルが非常に高いので、親族なら一般的な扶養義務があることから、よほど明確で大きな貢献でなければ「特別」とは認められにくいです。
また、他の相続人との間で新たな相続争いが生じるのを避けたいと考える方が多いため、寄与分を主張される方は少ないのも事実です。
しかし、遺産分割協議をする上で、まずは寄与分を主張することは大切なことです。そして意見対立などがあり、協議で金額を決められない場合は、家庭裁判所の調停・審理手続きの中で決める必要があります。